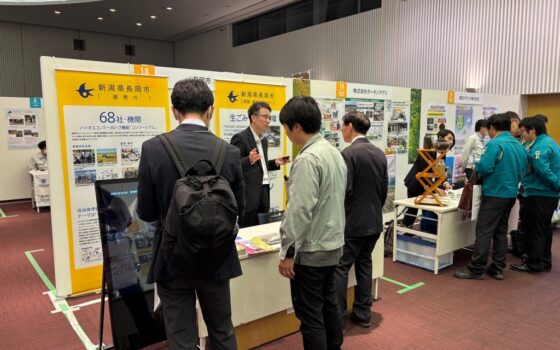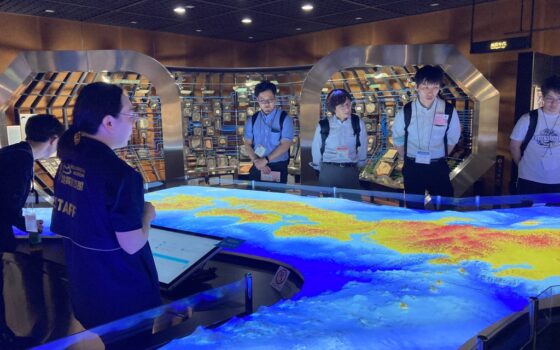新潟県長岡市の街中から車を30分ほど走らせるとたどり着く、山古志地区。美しい棚田が広がる山に囲まれ、冬には数メートルの雪が積もる豪雪地では、錦鯉や闘牛など独自の文化が育まれてきました。2017年3月には「雪の恵みを活かした稲作・養鯉システム」が、農林水産省による「日本農業遺産」に認定されています。
日本の原風景が今も残る山古志で、昔から受け継がれてきた野菜があります。
その名も「かぐら南蛮」。
南蛮(なんばん)とは、「とうがらし」のこと。戦国時代の頃に日本に渡来したと言われ、全国各地で作られているとうがらし。多くの方が細長いシシトウをイメージすると思いますが、山古志の「南蛮」はピーマンが横に四角く膨らんだような形が特徴。シワの寄ったゴツゴツした見た目が神楽面に似ていることから、「かぐら南蛮」と呼ばれるようになったと言われています。
肉厚の果肉自体はそれほど辛くなくほのかに甘みを感じるのですが、種とその周囲の白いワタには強い辛味があります。その独特の味は地元の人々に昔から親しまれ、今では長岡市を代表する野菜の一つとなっています。
山古志の地で独自の進化を遂げた「かぐら南蛮」が、どのように作られ、受け継がれてきているのか? 種を守り続けてきた「山古志かぐらなんばん保存会」の会長・青木幸七さんを訪ねました。